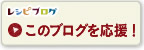9日目 フランス
ブフ・ブルギニョン (beef Burgundy / bœuf a la Bourguignonne)
“牛肉の赤ワイン煮込み” です。
フランスのブルゴーニュ地方の郷土料理だそうです。
ブルギニョンはブルゴーニュからきているんですね。
ちなみに、鶏肉の赤ワイン煮込みは”コック・オ・ヴァン”というらしいです。
これもまた機会があれば作ってみたいです。
記念日やイベントの際、プレゼント交換する…みたいなお祝いはしませんが
クリスマスが近づいてくると作りたくなるのがこの料理。
贅沢な料理が食べたい!という時に作りますが、元々は庶民料理だったそうです。
(貧しいブドウ農家が安いワインで牛肉を煮込んで食べたのが始まりだったとか)
なんてリッチな庶民料理なんだ…
ベルギーは黒ビール煮、フランスは赤ワイン煮
使用するお酒にその国のカラーが反映されていて興味深いです。
日本だと…なにに当たるでしょう。酒蒸しとか?
牛肉の煮込みと言えば、鍋でじっくり長時間煮込む…というイメージですが、
私は低温調理バージョンにアレンジして作りました。
本場の味とは異なると思いますが、
少しでも参考になる部分があれば幸いです。
それではレシピをば。
材料・作り方
【材料】
牛肉 肩ロース 200g (角切り)
マッシュルーム 6〜8個 (スライス)
にんじん 1本 (お好みにカット)
たまねぎ 1個 (お好みにカット)
赤ワイン…500cc
塩…全体量の1%
無塩バター…大さじ2
【作り方】
①赤ワイン500ccを火にかけ、アルコールを飛ばして冷やす
②ジップロックにカットした材料と①、ローリエを入れる
全体量の1%の塩を入れて全体を混ぜ、1晩寝かせる
③無塩バター大さじ2を加えて、85度で2時間以上加熱する
(すね肉の場合は3時間以上)
④加熱後、液体をフライパンに出して加熱 (その間具材は85度で加熱)
ペクチンについて 小話
今回温度を85℃に設定していますが、
その理由は野菜を一緒に調理しているためです。
大雑把に説明すると、
野菜には「ペクチン」という糖が含まれてまして、
細胞同士をくっつける働きを持っています。
このペクチン、温度によって硬さが変化する性質があり
50〜60℃では硬く、80〜90℃では柔らかくなります。
つまり、野菜炒めやサラダなど、野菜の歯ごたえを
しっかり残したい場合は低温で加熱するのが◎。
煮込み料理のように、くたくたに仕上げたい場合は
ある程度高温で火を通すと◎。
ということになります。
今回はまさに、くたくたに仕上げたい&野菜の出汁もほしい
ということで85℃に設定しました。
ちなみに、肉のコラーゲンが軟化し始める温度も75〜85℃です。
コラーゲンは65℃で収縮を始め、75〜85℃で軟化します。
水分を保って柔らかく仕上げたい場合は65℃以下
ホロホロと崩れる様な柔らかさに仕上げる場合は75℃以上
で加熱すると◎というわけです。
さらにさらにもう1つ、
ペクチンを利用した食べ物としてジャムが挙げられます。
作りやすい果物、作りづらい果物があるのはペクチンの含有量の違いによるものです。
リンゴやブドウ、ブルーベリーなんかはペクチンが多い果物ですね。
ペクチンが少ない果物のジャムも存在しますが、
その場合はゲル化剤が添加されていることが多いかと思います。
…ということで、話が逸れまくりましたが、
作りたい料理に合わせて温度管理をすると確実に美味しいご飯が食べられる!
という小話でした。(赤ワイン煮込みどこいった。)
**********
…当企画について。
日本から出たこと無い人間が自宅で世界の料理を作って
旅行気分を味わおう!と始めた1人企画。
私は基本的にお肉は低温調理しているので、
本来揚げたり焼いたりする料理も低温調理でアレンジします。
味の再現はできる範囲でやっていますので、レシピを見て
入手が面倒そうなスパイスや食材は省くか、代わりになるものを使用します。
あくまで”○○風”ですので「その調理法だと定義から外れてる!」的なのは
目を瞑っていただけると幸いです。
(海外旅行の経験は1度もないので、本場の味も何もないのです…)
ただ、本場で使われるスパイスやハーブ、調味料、食材の情報は
とても興味がありますので、教えていただけると喜びます。